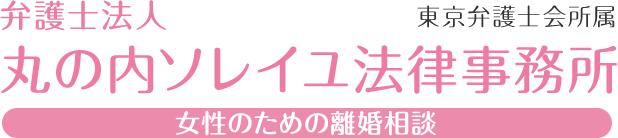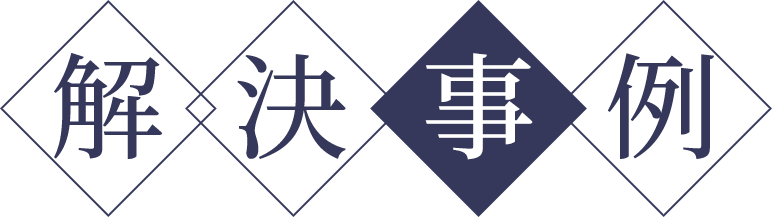目次
年金分割とは
離婚の際、その後の経済的な問題を考えたときに、財産分与と同様に考えるべきが「年金分割」です。専業主婦の方、ご主人の扶養内で働いている方など、年金はご主人の年金に入っている方が多いでしょう。ここでは年金の分割について、ご説明します。
年金分割の種類
現在日本では厚生年金について年金分割という制度が認められています。厚生年金に対する年金分割は社会的な制度としてルールが定められておりますので、現在、現時点では裁判所に申し立てをすれば0.5の割合で分けられるということになっています。
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 施行日 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
| 対象になる離婚の時期 | 平成19年4月1日以降の離婚 | 平成20年5月1日以降の離婚 |
| 按分割合 | 夫と妻の標準報酬総額の2分の1以下の範囲内で、合意で定める。 | 標準報酬総額の2分の1(法定) |
| 分割の対象期間 | 婚姻期間(施行日前の期間も含む)。 | 平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間。 |
|
*1 結婚した月から離婚した月の前月までが年金分割の対象期間となりますので、3号分割は制度施行(平成20年4月)の翌月(平成20年5月)以降の離婚から対象になります。 *2 障害年金を受給している人から分割を受けることはできません。 |
||
年金分割の算出方法
就業状況によって、分割の対象になる金額や計算方法は異なります。本項では、共働き、専業主婦、自営業の3つのケースについて説明します。
共働きの場合
共働きで、夫、妻それぞれが厚生年金に加入し、その受給権者となっている場合、各自が婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料が、相互に年金分割の対象になります。もっとも、年金分割の対象はあくまで厚生年金の納付済保険料であるため、共働きといっても、例えば結婚後、妻は夫の扶養内でのパート勤務で自身は厚生年金に加入していなかった(第3号被保険者)という場合は、夫の厚生年金の納付済保険料のみが年金分割の対象になります。
専業主婦の場合
専業主婦で、平成20年5月1日以降に離婚した場合、平成20年4月1日以後に第3号被保険者であった期間については3号分割の対象になり、年金事務所に請求すれば、相手方の合意がなくても、自動的に厚生年金の納付済保険料の2分の1が分割されます。ただし、平成20年4月1日より前の期間については、3号分割の対象外ですので、別途按分割合を取り決めて、合意分割を行う必要があります。
自営業の場合
わが国に年金制度は、3層構造になっており、国民年金(老齢基礎年金)が1階部分、会社員や公務員に対して支給される厚生年金・旧共済年金が2階部分、これらの公的年金に加えて、さらに上乗せされる企業年金等が3階部分とされています。このうち、年金分割の対象になるのは2階部分である厚生年金・旧共済年金の納付済保険料であるため、これらを持たない自営業者の場合は分割対象となる年金がなく、年金分割を行うことはできません。
年金分割手続きの流れ
年金分割の手続をどのように行うかは、合意分割、3号分割のいずれを請求するかにより異なります。
合意分割の場合
合意分割では、夫と妻が年金分割をすること及びその按分割合について合意し、合意ができなければ、当事者のいずれかが家庭裁判所に調停や審判の申立てをして、裁判所が按分割合を決定することになります。
協議
年金分割をすること及びその按分割合(上限は2分の1)について、夫と妻が話合い、合意します。離婚後、年金事務所において年金分割の手続をする際には、当事者が作成した「年金分割の合意書」を提出します。手数料はかかるものの、離婚前に公正証書を作成しておくとより安心です。
調停(調停の申し立て)
年金分割の合意ができない場合、離婚前であれば離婚調停を申し立て、当該調停に付随して年金分割も申立てます。離婚後であれば、離婚成立日の翌日から2年以内に、家庭裁判所に、年金分割の割合を定める調停を申し立てることができます。
必要な書類・費用
審判
家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判を申し立てることができます。申立先は、申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。家庭裁判所は、申立てがあると相手方の意向を聞くための照会書を送り、特段の事情がない限り、書面審査のみで按分割合を決定します。
3号分割の場合
離婚後、第3号被保険者であった者が、年金事務所に請求すれば分割の手続が行われます。3号分割では、按分割合は2分の1に法定されており、2分の1で強制的、自動的に分割されます。よって、合意分割のように夫と妻が合意して按分割合を取り決めたり、裁判所に按分割合の決定を求める必要はありません。
年金分割には時効があります
原則として、離婚成立日(判決離婚の確定日、調停離婚の成立日、協議離婚の届出日)の翌日から2年を経過すると、年金分割の請求はできなくなりますので、注意が必要です。
よくあるご質問
離婚における財産分与のお悩みは
丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください
 丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1000件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。
離婚における財産分与は、単純なようで複雑であり、弁護士の交渉力次第で結果は大きく変わってきます。
また、当事務所では、単なる法律相談ではなく、「心」と「頭」に満足いただくカウンセリング型相談を実施しております。
ご相談いただいた方々からは
「戦略的なアドバイスで、心強かったです」(50代会社員)
「一筋の光が差してきたような気が致しました。」(50代)
「本当に親身になってくれました」(50代 主婦)
というお声を頂戴しております。(ご相談者様の声はこちら>>)
丸の内ソレイユ法律事務所では、代表弁護士の中里妃沙子をはじめ、弊所に所属する弁護士全員が離婚や男女問題に関する相談に精通しております。
女性のお客様は初回60分無料ですので、離婚をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせ下さい。


離婚無料相談実施中


- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます