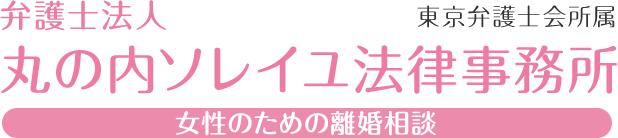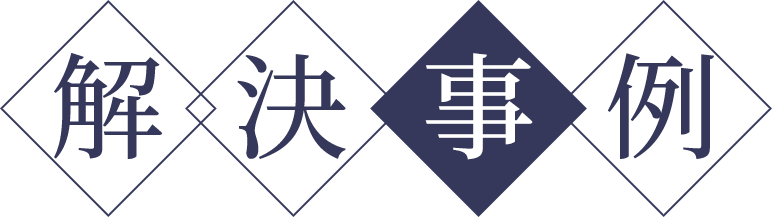目次
子の監護者の指定、引渡しとは
子を実際に監護する権利を監護権と言います。離婚協議中は共同親権ですが、夫婦が別居していれば、原則として、夫婦の一方のみで日常の監護を行わざるを得ません。子の監護をどちらが行うか夫婦間で協議が調わない場合に利用されるのが「子の監護者指定」や「子の引渡し」の手続です。
調停ではなく大半が審判
婚姻費用や面会交流の事件は、まずは調停にて話し合いを行い、話し合いが調わなかった場合に審判手続に移行するという運用がなされています。一方で、子の監護者の指定や子の引渡しの事件については、どちらか一方を監護者と定めなければならないため、初めから審判を申し立てます。
審判前の保全処分について
相手方が今にも子供を外国に連れ出そうとしているような場合が典型例ですが、審判の確定を待っていては権利を実行できなくなるおそれがあるような場合には、裁判所が一応の心証をもって仮に監護者を指定し、子の引渡しを命ずることができます。これを審判前の保全処分といいます。
子の監護者指定、引渡し審判の流れ
子の監護者指定、引き渡し審判の流れを順を追って説明します。
審判の申し立て
申立書を作成して、戸籍謄本や証拠書類と一緒に裁判所に提出をします。証拠書類として、「子の監護に関する陳述書」の提出を求められますので、申立ての際に作成するようにしましょう。
審判官調査
初回期日後は、家庭裁判所調査官による調査が行われることが多いです。調査では、申立人・相手方の面接(裁判所で行います。)、子ども本人との面接、家庭訪問が行われます。場合によっては、保育園や学校の先生から調査なども実施されています。
審判
双方の主張と証拠、調査官が作成した調査報告書を基に、裁判官は、監護者として父母のどちらが適切か判断し、審判をします。子の引渡しが認められた場合には、当該審判により強制執行の手続をとることが出来るようになります。
子の監護者指定・引渡し請求のポイント
早期の申立てが重要
監護者を指定する際、裁判所としては、現在の子の状況が子にとって問題があるかという点を重視します。相手方が子を連れて家を出てから数か月間放置してしまうと、裁判所が現在の相手方の監護に問題がないと判断する可能性が高くなりますので、申立ては速やかに行う必要があります。
夫が子の引渡しに応じない場合
強制執行
子の引渡しを命ずる審判が出たにもかかわらず、相手方が任意の履行に応じない場合には、裁判所に強制執行を申し立てることになります。
強制執行の方法には
- 間接強制(一定期間の引渡しがなければ間接強制金の支払いを命ずることで自発的な引渡しを促す)
- 直接的な強制執行(執行官が実際に債務者による子の占有を解いて債権者に引き渡す)
があります。詳しくは強制執行ページをご覧ください。
人身保護請求
子を監護している相手方が日常的に子に暴力を振るっている場合や子を家に閉じ込めて義務教育すら受けさせていない場合など、相手方の監護の違法性が顕著な場合には、人身保護法に基づいて子の引渡しを請求できる場合があります。
子の監護者指定・引渡し請求に関するご相談は丸の内ソレイユへ
弁護士による離婚解説動画


離婚無料相談実施中


- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます