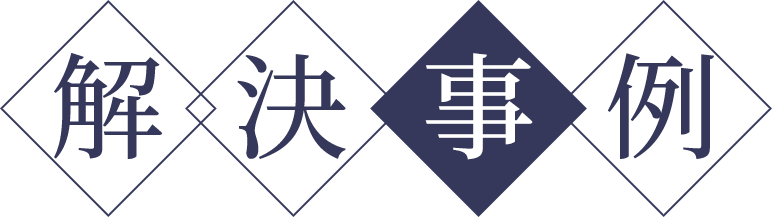日本の裁判所で手続きできる場合

外国人との離婚を考える場合、最初に考えなければならない点は、日本で離婚手続きを進めていけるか、という点です。いわゆる「管轄」という問題です。
この点については、「人事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成三〇年四月十八日成立、平成三十一年四月一日施行)により、立法化され、明確になりました。
この法律によると、以下のような場合には、日本の裁判所に離婚裁判を提起することができます。
- 相手方の住所地が日本国内にあるとき
- 当事者双方が日本国籍を有するとき
- 当事者双方の最後の共通の住所地及び原告の住所地が日本国内にあるとき
- 原告の住所地が日本国内にある場合であって
ⅰ.被告が行方不明なとき
ⅱ.被告の住所地のある国においてなされた離婚裁判の確定判決が日本で効力を有しないとき
ⅲ.その他日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められたとき
日本国内の場合以外でも、日本で離婚手続きを進めることができる場合がある
では、上の場合以外は、日本で全く離婚手続きを進めることができないのでしょうか。
この点については、右の人事訴訟法改正前の最高裁判所の判例などの実務運用が参考になるでしょう。
この点についての最高裁判例は、①相手から遺棄された場合、②相手が行方不明の場合、③その他これに準ずる場合には、原告の住所地の管轄を認めるとしています。
「その他これに準ずる場合」とは被告が応訴した場合やそもそも相手の住んでいる外国で婚姻自体が成立しておらず、離婚手続きができない場合などが考えられます。
いずれにせよ、改正後の人事訴訟法では、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められたとき」には、日本の裁判所の管轄を認めていますので、だめもとと思い、日本の裁判所に離婚裁判を提起してみることも一つの方法でしょう。
また、前述の改正法では、日本の裁判所が調停に関して管轄を有する場合として以下を挙げています。
- 離婚裁判又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき
- 相手方の住所が日本国内にあるとき
- 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることを合意したとき
相手方が外国にいる場合には、訴状の送達の仕方が問題となる

相手方が外国にいる場合、訴状の送達の仕方が問題となります。外国送達の仕方にはいくつか種類があり、相手方の所在が分かっている場合は、領事館を通しての送達(領事送達、民訴法108条)が原則となります。もっとも、裁判所ごとに異なる扱いもありえますので、訴状を提出した裁判所の書記官と相談するか、書記官の指示に従って下さい。
訴状を外国に居住している相手方に送達する場合には、数ヶ月を要します。実務例が多いアメリカでも、3ヶ月から4ヶ月、東南アジア諸国で半年から8ヶ月程度、ロシアに至っては、 1年以上要します。裁判の第1回期日は、訴状が相手方に送達されたことが確認された後に開かれますので、相手方が海外に居住している場合には、そもそも裁判所に訴状を提出してから実際の裁判が始まるまでにかなりの期間を要する点、注意が必要となります。
また、相手方が訴状を受領しないとそもそも離婚訴訟を始めることができないため、相手方に訴状を受け取るよう促したり、場合によっては、外国送達の手続と並行して協議離婚の可能性を探っていくことも有益と考えられます。
なお、相手方の所在が不明の場合は、外国公示送達という別の方法によることになります。
ところで、日本の裁判所で日本法を適用して裁判するとなった場合、調停前置主義の原則から、調停の申立てが必要となるのではないか、という疑問がわいたと思います。この点、家事事件手続法257条2項は、「前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。」としつつも、同項のただし書きにおいて、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。」と規定しています。すなわち、絶対にまず調停を申し立てなければならないわけではなく、事情によっては、いきなり訴訟を提起しても、裁判所が調停にせずにすぐに裁判手続きを進めてくれる場合もある、ということなのです。
相手が外国にいる場合には、そもそも調停を申し立てても相手が調停に応ずる可能性は少ない、ということを裁判所に説明し、直ちに訴訟を提起するとよいでしょう。
離婚に際して日本の法律が適用されるの?

日本で離婚手続きができるとして、適用される法律(準拠法)は、日本の法律なのでしょうか、それとも相手方の国の法律なのでしょうか。
「法の適用に関する通則法」27条、25条
準拠法を定めるには、法の適用に関する通則法27条、25条により、以下の順番であるとされています。
① 夫婦の本国法が同一であるときには、その本国法、
(例)ドイツ人夫婦の離婚→ドイツ法
② 夫婦の共通本国法がないときは、夫婦の共通常居地法、
(例)ともに日本在住の米国人夫と中国人妻の離婚→日本法
③ 共通常居地法がないときは、夫婦に最も密接な関連のある地の法律、
(例)日本在住の韓国人夫と、英国在住の英国人妻で、日本で知り合って結婚し、長年日本で生活してきたが、妻が英国に戻って間もなく離婚を求めてきた→日本法
④ ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律、
と規定しています。
常居所とは、単なる居所とは異なり、相当長期間にわたって居住する場所のことをいいます。上記の通則法の基準からすると、①→②→③によっても準拠法が決まらない場合で、夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合には、④に従い、準拠法は、日本法ということになります。
日本法が適用されるときは、協議、調停、裁判と進めることができる
日本法が規定する離婚の方法は、これまでご説明してきたように、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。したがって夫婦の一方が外国人の場合でも、日本で日本法に基づいて離婚する場合、協議離婚が可能です。相手方が離婚に同意している場合には、協議離婚が最も簡便な方法です。
協議離婚の場合には、離婚届を戸籍係に提出して離婚となり、調停離婚、裁判離婚の場合には、届出が報告的届出であることは日本人同士の離婚の場合と同様です。
日本にいる外国人同士の離婚の場合
この場合の準拠法も、上記「法の適用に関する通則法」の規定が適用されます。
すると、夫婦が同一国籍であれば、その国の法律が準拠法になります。夫婦の国籍が別々の場合には、夫婦がともに日本に住んでいますので、日本法が準拠法になります。
離婚と在留資格
日本人と結婚していた外国人の在留資格が、「日本人の配偶者」である場合、離婚によって直ちに在留資格を喪失するわけではありません。
しかし、在留期間が満了した場合には、「日本人の配偶者」の在留資格を更新することはできません。
その場合には、「定住者」への変更を求めることになります。
関連記事


離婚無料相談実施中


- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます